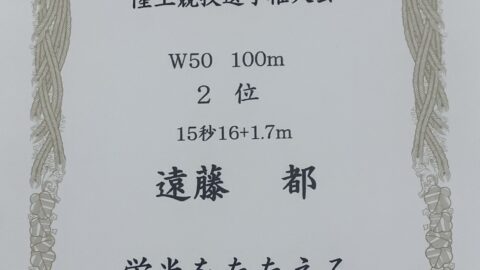心身症アスリート 完璧でない私の挑戦』③
自叙伝過去 エッセイ
『教訓 人生の中で、どうもしようがない時は、辛抱の時。充電期間でもある』
自宅療養となり、色々と病院に足を運んだ。
最終的に紹介状を持ち、名大病院(名古屋大学医学部附属病院)で『身体の機能は悪くなっていないので日にちが解決するものです』との解釈で私の病気は、謎のままで終わった。
治療法もなければ、病名も不明で、いつ治るのか、治らないのかもまったくもってわからない状況であった。
今なら『心の病』として扱われ、障がい者の手帳もいただいていたと思う。
頭を支えることができず、身体のバランスが悪いため、座れないし、まっすぐ立てないし、頭が重いので、頭をあげられない状態で、首と肩がひきつった状態で、腰を曲げて何とか歩いて、悲惨な感じであった。
その頃の一日の生活は、基本布団の中で仰向けになって寝ており、毎日涙をたくさん流した。一生分の涙を流したと思う。
『どうしてこうなったのか』『この状態はいつまで続くのだろう』『私は死ぬまでこのままなのか』という不安の思いと絶望感でいっぱいだった。
今思うと、この姿を毎日みている両親や芋はどんな思いだったのだろうか。
この時から私の家族の間に笑顔が消えた。
そして、家族の誰かが大きな問題を抱えると、心からの笑いは家庭から、無くなることも体感した。
寝たきり生活は、この後もまだ続くのだが、その時は、まだ私は、病を発症してからの月日が浅いため、不安や絶望はあったものの、自分の気持ちが『悲しみでいっぱい』であったために、心の苦しみが訪れる予知はしていなかった。
こんな状態なのに『この状況も試練のうち。困難を乗り越えて、もっと人間的にも大きくなって、オリンピック出場の夢を叶えるんだ。そのためにも早く治して、復帰せねば』と思っていた。
- まだ、陸上競技に固執をしていた。しかし、諦めていない気持ちが、生きる力になっていたことも確かなことであった。 続く